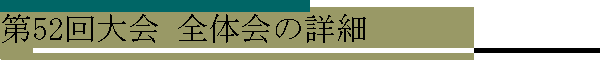
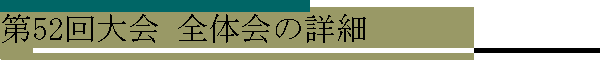
一九世紀欧米諸国は東アジアへの進出を本格化した。一八四〇年のアヘン戦争を例に挙げるまでもなく、それは武力行使も厭わない姿勢での進出であった。国際情勢が急変するなか、それまで中国を中心とした国際秩序の中にいた朝鮮は、まず日本に対して、ついで欧米諸国に対して開港した。
しかし実際には、激変していく状況に対して、朝鮮内部では多様な受け止め方がなされ、様々な議論が行われていた。そして、様々な形で行動に移されてもいるのである。このようないわば、輻輳的で動的な朝鮮の動きを、これまでの研究では未だに十分に描ききれていないのではないだろうか。
さらに言えば、同時期の研究は、分野ごとに切り離されて議論が行われてきた。その結果、それぞれの分野ごとに豊かな知見をもたらしたことは贅言を要すまい。今日に至って、その豊かな知見をもとに、領域横断的視野で見つめることも十分に可能になっているといえよう。
このような国際秩序の変化に対する朝鮮の対応に関してはこれまでも相当数の研究蓄積がある。また、近年多くの成果を上げている中国を中心とした国際秩序の変質を論じる議論の中でも、朝鮮は主要なアクターとして注目されてきた。しかしながら、その研究の多くでは、朝鮮の動向に関して、受動的かつ静態的に描かれてきた感が否めない。つまり、朝鮮独自の活動や積極的働きかけは、一部特定の事象を除いて等閑に付されてきたといえよう。
このような疑問に基礎をおき、本大会では、一九世紀中盤から二〇世紀初における朝鮮社会の変化を朝鮮の文脈で読み解いて行くことを目的とする。
国際秩序の急変を迎えた時点で、朝鮮社会がいかなる社会であったのかも、十分に解明されているとは言い難いであろう。朝鮮は日本や欧米諸国と中国の間におかれ、いかに独自性を発揮しながら秩序の再構築を模索していたのだろうか。そして変化の中で朝鮮は何を学び、いかに理解・消化し、変容させていったのか。
本大会では、しばしば指摘される開港後期朝鮮における経済的苦境の理由を探り(須川報告)、「交隣」の概念の変遷から日本や欧米諸国と結んだ国際関係の「新しさ」を疑い(姜報告)、条約交渉の中で発揮される朝鮮の独自性の表出を跡付けていく(李報告)。
以上の三つの報告を通じて、開港前後期の朝鮮の模索を浮き彫りにしていきたい。
![]()
![]()
近年、一八〜一九世紀における朝鮮の社会経済事情について、韓国の経済史研究者たちを中心として、新たな歴史像が提示されている。それは、従来の資本主義萌芽論およびその延長線上に構築されてきた一八〜一九世紀史像とは大きく異なっている。これまでは、一八世紀における資本主義萌芽≒近代的要素の検出と、商業的発展が重要な社会変化として論じられてきた。しかし、一八世紀における朝鮮社会の発展方向および為政者が構築しようとしていた朝鮮国家の方向性は、必ずしも商業的、市場経済的な発展を目指すものではなかった。そこでは、朝鮮半島の気候的環境に左右されてしばしば発生した飢饉を乗り越え、零細な農民たちの生活を安定させるための方策が重視されたのである。ことに一七世紀後半に発生した飢饉では数多くの犠牲者を出している。飢饉による社会的危機を回避するために採られたものが、還穀をはじめとして、米穀などの物資をあらかじめ大量に貯蔵しておくことであった。大量に発行され流通するようになった「常平通宝」もまた、その第一義的な発行目的は、米・布とならぶ価値の備蓄手段だったのである。
しかし、一〇〇〇万石にも及ぶ還穀は、その耗穀収入が財政収入に流用されるようになる。一八〇九頃からの飢饉の頻発は、備蓄された還穀を減少させたが、それは同時に財政収入の減縮をも意味した。他方、地力略奪的に行われていた農業はしだいに土地生産性を低下させる。のみならず一八世紀における人口増加と生活水準の向上は、農地拡大や管理する者のいない状態での木材乱伐、薪木採取増加により森林を荒廃させ、洪水頻発、水利施設の機能低下を招く。これらが複合して米穀の生産量は低下し、慢性的な食糧不足を招いた。さらに地方の商取引までもが委縮する。
米穀生産の低下にたいし抜本的な対策を取れなかった王朝政府は、従来の備蓄政策を固守し、財源としての還穀回収を強化するが、それは本来の賑恤目的ではなく、収奪の強化に他ならなかった。さらには財政収入を補填する目的で商品にたいする無名雑税を濫徴してさらなる物資輸送の委縮を招く。ついに銅銭の大量発行に踏み切るが、それはもはや物価上昇を加速させたに過ぎなかった。つまり、一八世紀において有効であった国家的再分配と備蓄の経済体制は、一八四〇年前後からは、むしろ桎梏と化し、開港という衝撃にたいし有効な対応策を奪う結果となったのである。
![]()
朝鮮が西洋近代国際関係に編入された後に、「事大」概念とともに近世朝鮮の国際関係を支えた「交隣」概念が如何なる歴史を経たのかは、いまだに明らかになっていない。本報告は、「交隣」概念が、近代に入ってもすぐに消えていなかった可能性に着目して、この概念の展開を追跡することで、東アジア国際関係の近代的な再編の過程で朝鮮が行った模索のもう一つの側面を明らかにすることを目指す。
朝鮮王朝前期から国家間の対等な関係性をも表していた「交隣」概念は、朝鮮王朝後期においては、「交隣」の精神的な根拠である「誠信」と結びつく一方で、その実像として前例が蓄積されるに至ったことで、具体性を増していた。
一八七六年の「日朝修好条規」の締結は、前例の部分が廃棄された点では「交隣」の断絶であったが、関係の対等性という核心的な内容と「誠信」の原理が受け継がれた点からいえば「交隣」の継承であった。
一八八〇年から始まったアメリカとの条約交渉の際に、「交隣」はこの外交活動において広く用いられることで、文明を超えた拡散を見せた。このような現象は、なによりも「対等な国家間関係」という「交隣」の原理が西洋近代国際関係の原理と類似していたことに起因するが、『万国公法』による西洋近代国際関係の理念型の理解とアメリカとの外交交渉による西洋近代国際関係の実際の理解という当時の独特な事情も関わっていた。
甲午の改革によって、政府における国際関係の概念が「外交」に集中されたことで、外交の現場において「交隣」は周辺化された。ところが、この時期から民間の活動における「交隣」の使用が増え始めた。とりわけ、第二次日韓協約以降は、西洋国際関係のもう一つの側面である権力政治による大韓帝国への侵略が本格化する中で、「交隣」は日本帝国主義への思想的な抵抗を可能にする概念として、斥邪派から日本留学生に至るまで、広く用いられた。「交隣」が伝統的な概念であると同時に近代的な概念でもあったことが、このような広範な政治的使用の原因であった。
ところが、「交隣」の政治化は、忘却への道の始まりでもあった。植民地化を国際関係における道徳の無力さの証明と理解した人々は、道徳性を否定する立場から「交隣」を否定したし、植民地化によって儒教の弱体化がさらに進んだことで、帝国主義を批判する立場の人々は「交隣」にこだわることなく、西洋の概念を使う傾向が広がりを見せたことで、ついに「交隣」は死語になった。
![]()
本報告は一九世紀後半の日朝関係における朝鮮の主体的動向を考察し、朝清間の宗属関係がまだ有効であった同時期に、朝鮮が日本との外交において戦略的な事大主義政策を駆使したことを究明しようとするものである。
従来一九世紀後半の東アジア国際関係においては、日清両国を中心に分析が行われてきた。朝鮮を独自の主体として把握する視角に欠ける傾向があり、日朝関係史においても日本の対朝鮮政策の様相は緻密に検討されてきたのに対して、朝鮮の動向はあまり注目されず、朝鮮に相当の影響力を発揮していたとされる清の動向に関心が向けられてきた。
こうした研究傾向に対する批判として、最近朝鮮の自主外交の実態を究明する研究が進んできたのも周知のことである。これらの研究は、主に宗属関係下の朝清関係を対象にして、朝鮮が清の属国という立場にありつつも、「自主」外交を追求していく側面を明らかにした。
一方で、隣国日本とのあいだで朝鮮がどのような外交を展開していったかに関する研究はそれほど多くなかったように思われる。しかし、日本は華夷秩序の外に位置していたため、朝清関係と違って、日本との条約関係では宗主権の影響力が及ばない領域が存在し、そのなかで朝鮮の主体的動向をより浮き彫りにできると考える。そこで、本報告では朝鮮を中心として、朝鮮の立場から日朝外交史を描くことにしたい。その際に、一つの事例を緻密に検討するよりは、一八七六年から一八九三年までの時期という長いスパンで朝鮮外交の動向を考察する。
時期設定に関して、一八七六年を起点としたのは朝鮮が日本と日朝修好条規を結んだ年であり、それを契機に朝鮮は次第に万国公法的な外交体制に編入されていくようになったからである。終点を日清戦争直前の一八九三年にしたのは、日清戦争によって清が日本に敗北し、その結果宗主国としての地位を失ったことで、その後の朝鮮外交に介入する名目がなくなったからである。つまり、本報告では、朝鮮に対する清の宗主国としての影響力が公式的に有効であった時期を対象にして、朝鮮が清との宗属関係下にありながら、どのような対日外交を展開していたかを検討する。その際に朝鮮が戦略的な事大主義政策を駆使したことを明らかにしていく。それを通して一九世紀末の東アジア関係史に対する理解が深まることを期待したい。
![]()