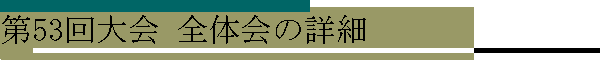
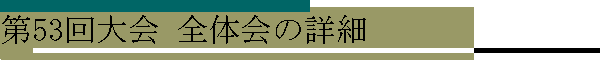
一七〜一八世紀の朝鮮は、一六世紀に本格化する社会変動、壬辰・丁酉の乱、丁卯・丙子の乱を受けて従来の体制が再編された時代と位置付けられる。中央・地方軍の再建、大同法さらには均役法による財政改革、そして日本との通交再開などがその代表的なものといえる。
こうしたなか、朝鮮の対清関係のみはそうした問題関心から取り残されてきた。単純に対明関係と同様の冊封関係であったものと論じる傾向が依然として続いている一方、清の侵略により成立した関係であるため、朝鮮が常に弱い立場であったとする議論もみられる。朝鮮の対清関係の実像は長く曖昧なまま、主たる研究対象となってこなかった。
しかしながら、対明関係と対清関係を単純に同一視することはできない。制度的な面では、対清関係には歳貢(歳幣・年貢)や国境での互市など対明関係にはみられなかった関係がある。思想的な面でも、小中華思想の高揚、ひいては「朝鮮中華主義」の成立などが強調されてきたが、満洲人の手になる清もまた「夷」と「華」の葛藤を抱えていたことは十分に踏まえられていないように思われる。清との関係は朝鮮にとって最も主要な外交関係であり、その実像を見極めることなしに、一七世紀以降の朝鮮社会再編の意義を理解することは難しいだろう。
そこで本大会では、近世朝鮮の対清関係を再考するために、特に一七〜一八世紀、清との関係の構築時期に焦点を当てたい。まず鈴木報告では、丙子の乱に際して清皇帝が降服条件として下した「詔諭」を分析し、朝清関係成立の事情を明らかにする。続いて木村報告では三藩の乱時期における朝鮮から清への日本情報の通報に対する分析を行い、当時の国際情勢と、そこにみえる朝鮮の対清外交姿勢について検討する。最後に文報告では、『大義覚迷録』に対する朝鮮知識人の反応から当時の清をめぐる朝鮮の思想状況について考察する。以上の三報告を通じて、朝清間の制度の形成、運用、そしてそれらを踏まえた朝鮮の思想や世界観を明らかにしていきたい。
昨年に引き続き、揺れ動く国際情勢・国際秩序における朝鮮の対応を扱うことになる。近世朝鮮の対清関係の実像が明らかになることによって、昨年対象とした開港前後期の外交関係を新たな視点で捉え直すことも可能となるであろう。また、コメンテーターとして清朝史の立場から杉山清彦氏、ベトナム史の立場から岡田雅志氏をお迎えすることとした。同時代の清を中心とする国際秩序や、ベトナムと清の関係といった観点から朝鮮と清の関係を見直すことで、その特色がさらに明確になるだろう。
![]()
![]()
仁祖十四年(一六三六・崇徳元)の清による第二次朝鮮侵略である丙子の乱は、朝清関係の成立という意義をも有している。しかしながらこれまで、朝鮮史の側からこのことについて自覚的に取り組んだ研究はほとんどなかったように思われる。
既存の韓中(中韓)関係史の研究でも、この戦乱は当然のごとく言及されたが、例えば全海宗氏の「典型的朝貢関係」論では高麗・朝鮮と明・清の関係の同質性が強調されるため、その意義は低く評価される。全海宗氏の著書『韓中関係史研究』(一潮閣、一九七〇年)には、仁祖五年(一六二七・天聡元)の丁卯の乱に対する論考は収められているものの、丙子の乱に対するものは収められておらず、丁卯の乱によって朝清関係が成立したとする印象を抱かせられるものとなっている。また、台湾の張存武氏もその著書『清韓宗藩貿易一六三七〜一八九四』(中央研究院近代史研究所、一九七八年)において、丙子の乱によって「清韓宗藩封貢関係」の制度が定められたとしながら、別の著書『清代中韓関係論文集』(台湾商務院書館、一九八七年)では、「明清両代」の「中韓関係」は「中国を中心とする封貢外交」の「典型」であったとして全氏の所論を踏襲するなど、その見解には揺れをみせている。
要するに全氏の研究を継承した崔韶子氏が「清国との関係」(『韓国史』三二、国史編纂委員会、一九九七年)において仁祖二十二年(一六四四・順治元)の清の入関後、「朝鮮と清の関係は正常化」したと述べたように、これまでは清の入関以前の朝鮮と清の関係をいわば例外の時代と位置付ける非歴史的な見方が主流であったといえる。本報告では、以上のような見方を排して、ごくごく素直に丙子の乱を朝清関係の起点と捉え、どのようにして両者の関係が結ばれたのかという点を明らかにする。
とはいえ、丙子の乱それ自体に対する研究も史料的制約から十分に進んでいない。そこで報告ではまず、戦乱の経過について基礎的な検討を行い、その概要を示した上で、清のホンタイジから仁祖に対して下された「詔諭」にみえる降服条件がその後の朝清関係においてどのような意味を持ったのかについて考察する。
本報告の試みは、かつて篠田治策氏が『南漢山城の開城史』(一九三〇年)において行った試みと近いように思われる。しかしながらこの著作は副題に「極東におけるCapitulationの一例」とあるように近代的な枠組みに引き付けて理解しようとする傾向があった。さらに、清の目的が完全に達成されたとしてその分析を終えるなど歴史的実態を追究しようとする姿勢に乏しく、以後の研究に影響を与えることもなかった。本報告は篠田氏の研究とも一線を画し、これまで報告者が行ってきた朝鮮・後金関係に対する研究を踏まえ、朝鮮・後金関係と朝清関係の連続性を強調し、朝清関係を再考するための端緒としたい。
![]()
本報告では、呉三桂の反乱から台湾鄭氏の降伏前後の時期の朝清関係に、日本の情報収集がもたらした影響を検討する。三藩の乱発生により、明朝の復興を期待し、北伐論が強まる朝鮮と、朝鮮も反抗するかも知れないと疑う清は、相互に不信感を抱えていた。三藩の乱発生以降、朝鮮は清、日本の両方と外交関係を持っていたため、清、日本双方から情報を収集していた。朝鮮は基本的には年に一度北京に使節を送っているため、北京や中国北部で情報を収集することができたが、反乱が起こっている中国南部の情報を収集するのは困難であり、対馬からも情報を収集していた。長崎経由で南方からの情報を収集している日本は、三藩勢力や台湾鄭氏の動向を知る上で重要な情報源であった。一方日本と清は、外交関係を持っていなかった。情勢を注視する日本は、長崎に来る商人や、清に朝貢に行く琉球使節から情報を得る以外に、対馬を介して朝鮮からも情報を収集していた。長崎や琉球からは南方の情報しかあつまらず、朝鮮からは清側の情報を収集できるためである。対馬は倭館での情報収集だけではなく、朝鮮朝廷に書契を送り情報を問い合わせることもあった。
朝鮮はこの書契について「倭情」として清に報告し、対清外交に利用する。日本側には隣好に感謝する一方、清には日本の脅威を強調して報告した。この情報を利用し、禁止されていた朝鮮国内の城郭の修理を進めるためである。しかし清側は三藩の乱開始以降、朝鮮の動向に不信感を抱いていた。そのため、この報告は城郭を修理するための口実と受け止められたが、この際は大きな問題にはならず、返事の咨文では情報を伝えたことを褒められた。また朝鮮から人を対馬に派遣して、日本に呉三桂側に加担させないようにさせるよう命じた。朝鮮側は清の指示を受け、対馬に対し訳官の書契の形で清の進軍情況を伝えたが、清から指示を受けたことには一切触れなかった。
この期間、朝清関係は相互に不信感を抱え、様々な事件により徐々に摩擦を高めていった。当初は問題が起きても、清側は朝鮮に罰を課すのを免除していたが、三藩の乱の主要な勢力が鎮圧されて以降、清は問題が起きると制裁的態度に出るようになる。『大清一統志』の地図を作成するため派遣された官人が国境地帯で朝鮮人越境者に狙撃されるという事件が起きると、この事件の処理の過程で謝恩使が提出した呈文が清側の大きな怒りを買い、朝鮮側が非常な屈辱と感じるほどの咨文を送って批難する。朝鮮側の今までの不誠実な態度が列挙されたが、この中で、日本は侵略の挙が無いのに妄りに奏上を行ったと、断定されるに至った。
![]()
本報告では,雍正年間に起きた謀逆事件の顛末をまとめた『大義覚迷録』に対する朝鮮の知識人たちの記録を通じて、彼らの対清観および華夷観について考察する予定である。
朝鮮の知識人による対清認識の基本的な枠組みは、崇明義理論による北伐論と、華夷観による崇明排清観である。しかしこれまでの研究から、こうした認識も時代の推移とともに変化していることが指摘されている。特に対外認識の変化として指摘されるのが、十八世紀後半から台頭してくる北学派の視点である。ここで取り上げる『大義覚迷録』は、この北学派が徐々に出はじめた時期にあたる雍正年間に刊行され、雍正帝の命により全国各地の役所、学校に配られ、次の乾隆帝即位とともに禁書となった書物である。ここには、一七二八 (雍正六、英祖四)年に、明末清初の朱子学者呂留良(晩村、一六二九-八三)の詩文を読み感化された曾静(一六七九-一七三六)が、彼の弟子とともに企てた排満の謀反に対して、雍正帝自らが訊問した記録と供述、事件に関する一連の上諭などがまとめられている。内容的には、曾静を謀反へと向かわせた呂留良の華夷思想と雍正帝即位の疑念、主にこの二点を雍正帝自ら論破し、清朝の中原支配の正当性を主張したものといえる。朝鮮には、刊行二年後の一七三二(英祖八)年に燕行使節を通じて伝来された記録が韓徳厚(一七三五-?)の『承旨公燕行日記』にみえる。
『大義覚迷録』で注目される点は、雍正帝が主張する華夷観である。彼は、「華夷之辨」に関して、「華」と「夷」の区分の基準は、出自ではなく仁義、五輪、礼法など儒教的な徳目が備わっているかどうかによると主張する。こうした華夷観は、朝鮮後期の変化として注目される洪大容(湛軒、一七三一-八三)や朴趾源(燕厳、一七三七-一八〇五)などいわゆる北学派や李瀷(星湖、一六八一-一七六三)など近畿南人派の華夷観と通じるものがある。同時にこの書に書かれている呂留良の伝統的な朱子学的華夷観も韓元震(一六八二-一七五一)など老論派にみられる華夷観と一致する。これまでの研究では、主に北学派と雍正帝の華夷観が注目されてきた。そこで、本報告においては、ます朝鮮における『大義覚迷録』と呂留良に関する記録をまとめ、つぎに特にこの書に関心を寄せた李*(信卿、一七三七-九五。*は土+甲)の記録を通じて、『大義覚迷録』という書籍の受容の様相を明らかにし、そこにみる華夷観と対清観を考察する予定である。
![]()